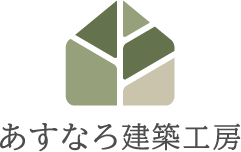2024年10月23日 設計
設計AIの現在地 Ver2
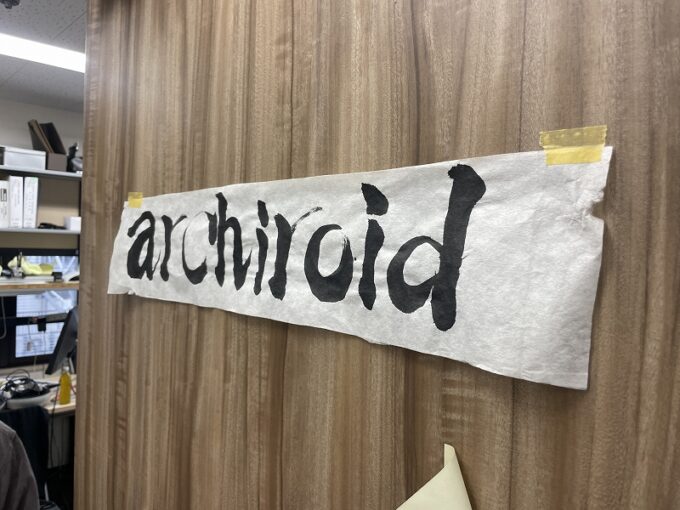
アーキロイドさんの事務所にお伺いしてきました。
9月18日のブログで「設計AIの現在地」のお話をさせて頂いております。
私自身もAI事情が気になってならなかったところに、アーキロイドの藤平さんから「意見交換会しませんか」とお声かけ頂き、事務所に訪問させて頂いてきました。
アーキロイドさんの名前の由来は、「ARCHITECT(建築家)+ ANDROID(人造人間) = ARCHIROID」だそうです。
「アルゴリズミックデザインで、建築の設計を自由にすること」が会社理念となっています。
アルゴリズミックデザインとは、「アルゴリズム(問題を解くための「手順」)に従ってデザインを行う手法」のことだそうです。
慶應義塾大学FSC教授松川先生の言葉を借りると「あらゆる自然現象の背後には必ず物理法則があるのと同じように、モノのかたちの背後にもある法則性がある。その<かたち>の背後に潜む法則性、つまり、<かたち(形)〉の<かた(型)>を見定めて、その<かた>をコンビュータプログラムへと書き下すことによって、<かち(価値)>ある<かたち>を探索すること」とのこと。

本日はそのアルゴリズミックデザインの考え方、現時点での具体的な活用方法、将来の可能性などをお伺いさせて頂きました。

9月の座談会の際にお話をお伺いしたことにプラスして、今回はVR(Virtual Reality)の体験もさせて頂きました。
実際に鎌倉で建設中のお家の3DモデルをVRゴーグルを着用して体験させて頂きました。
体験した感想は「もう現実にかなり近い。リアルに近い条件でシミュレーションが出来る。」というものです。
3DCADで作成した建物内と敷地内のデータ(近景)と建設前の実際の敷地で採取した隣地の3Dポリゴンデータ(中景)とグーグルアースから得られる遠方のデータ(遠景)とを組み合わせることで、相当にリアルなVR体験が出来ます。
ゴーグルを着用して、その場でかがめば、窓の外の景色が自分の姿勢に基づいてリアルに変わっていきます。
お隣の窓との目線、通りとの目線、遠くのマンションの廊下からの目線を事前に確認できます。
眺望の取入れ方も分かりやすい。
庭に植えた近景の樹木と、中景となるお隣のお庭の緑、さらには遠くに見える山の緑のシークエンスの様子を室内からの目線を移動させながら確認できます。
室内の3Dデータもテクスチャーを貼り込んであるので相当にリアル。
吉村順三さんの「畳める椅子」の裏側までしっかり再現されていました。
VR上のリビングのソファ(実際には会議室の椅子ですが)に座って顔を左に向けると、ダイニングやキッチンの様子が分かり、右に顔を向けると窓の外の緑が見えます。
そこに心地よい風でも吹いてくれば「そこに居るのではないか」という錯覚まで覚えてしまうレベルでした。
ここまでくると「もうリアルの建築はいらなくなるのかも?!」と思ったりもしてしまいました。
実際には4畳半一間のアパートの一室でこのVRを付けていても、バリ島の高級コテージに居る感覚を得られることも可能です。
映画の「アバター」や「マトリックス」の世界ですね。
そんな「リアルの建築物不要」な日も近いのかもしれません。
先日の座談会での報告でも書いていますが、設計AIはかなりのところまで来ています。
簡単な間取りと窓の位置を入力さえすれば、建築図面が自動的に出来上がります。
過去の建築データを読み込ませてあげれば、あっという間に過去のデータから得られた情報を元に3Dモデルも立ち上がります。
アーキロイドに参加している福井典子さんの設計事例は、既にインプットされているので「福井典子モデル」は自在に出来上がります。
3Dモデルが出来あがるだけでなく、平面や断面図や家具図などの図面も瞬時で出来てきます。
建設地の住所や概要もインプットされているので、法規チェックも自動でなされ、確認申請図も自動で出来ます。
「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」通称グレー本の内容を覚えさせてあるので、許容応力度計算も瞬時になされています。
言わずもがな、外皮の仕様などの過去の事例を覚えさせてあるので、UA値計算や一次エネルギー計算も瞬時に終わっています。
位置データも入力していますので、日射シミュレーションなんてお手の物です。
建設資材の数量の拾いも行われているので、建物の見積金額も瞬時にはじき出されます。
今まで当たり前のように繰り返し行ってきた単純設計作業は、AIが瞬時にやってしまいます。
Wallstat(木造住宅倒壊解析)との連携はこれからとのこと。
先日SAREXのワークショップで中川先生に、アーキロイドさんの開発AIについてお話したところ大変興味を持っていただきました。
連携される日はかなり近いと思います。
もう一つ、新住協のQ-PEX(暖冷房燃費計算プログラム)との親和性も高いと考えています。
まだ鎌田先生や久保田代表理事にはお話出来ていないので、近々お話したいと考えています。
実際の住宅の建材数量データや建材価格データなどは、JBN全国工務店協会の仲間の力を借りての情報収集が出来ると思います。
このアーキロイドさんの設計AIに、WallstatとQ-PEXと建材価格情報データが組み込まれると、住宅設計の最強ツールが出来上がると思います。
住所など土地の情報と間取りと窓の位置を入力さえすれば、瞬時に「確認申請図書」「温熱計算」「構造計算」「省エネ検討」「3Dシミュレーション」「見積」が出来上がります。
その評価軸の重み(評価指標)を持たせるのは、施主や設計者となります。
もちろんそこ(評価指標の重みづけ)もAIが最適解を出してくる日も近いかもしれません。
中川先生や構造塾の佐藤さんが目指している「誰も死なない家」や鎌田先生が目指している「皆が快適に住まえる家」が、この日本で普通になる日が近いように感じています。
弊社の設計スタッフには話をしていますが、この設計AIが簡単に出来てしまうもの、具体的には「CAD入力」「温熱計算」「構造計算」「法規チェック」「見積拾い」などの設計作業は、数年でAIに仕事を取られてしまいます。
それら仕事はかなり近い将来にAIがしてしまいます。
クリエイティブな仕事、つまりはAIを使う立場になっておかないと将来仕事が無くなってしまいます。
この設計AIの説明に、以前はアーキロイドさんも「初音ミクの設計版」と説明していたそうです。まさに住宅設計の「初音ミク」がこれから起こる予感がします。
アーキロイドさんが設計AIの設計プログラムを公開することで、いろいろな人が初音ミクを使ったボーカロイド的な建築を作り出し、作曲作詞が行われるように住宅の設計が行われるようになるのではないか。
設計者の中には「AIに仕事を取られてしまう」と思う方も多いことと思いますが、ボーカロイドがそうだったように、全部取られてしまう訳ではないと思います。
音楽業界では初音ミクの発明から、ボカロならではのヒット曲が生み出された一方で、ボカロP出身の作曲作詞家も生まれました。
米津玄師やYOASOBIがボカロ出身のアーティストとして活躍されていますよね。
設計AIの使い手が、今までにない設計による建築を生み出していくことが大いに予想されます。

本日の意見交換会では、この設計AIが設計業界のプラットフォームとなることをお願いしてきました。
この設計AIが誰でも使えるようになると、一般の方も設計の人もデータを入力をして家づくりのツールにするのではないかと思います。
どこかのメーカーやコンサルのお金儲けツールになってしまわぬよう、皆がこの恩恵を享受できるものになってもらいたい。
アーキロイドさんには、ここから得られるビッグデータを使って商売いただければよいのではないか。
意見交換会の最後には、浜松町にある中華料理屋さんでアーキロイドの皆さんとランチしてきました。
若い設計者(創造者?)の頭の柔らかさに、もうおじさんは付いていけないことを実感してきました。(^^;
AIに仕事を取られないよう頑張らなくては。
本日の意見交換の後は、アーキロイドの皆様とランチもご一緒させて頂いてきました。
ありがとうございました。
他の記事をみる