横浜市で狭小住宅を建てる際に注意すべきことを紹介!後悔しないためのポイントとは
「横浜市で狭小住宅を建てられるの?」というお悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。
狭小住宅とは狭くて小さな土地に建てる住宅のことで、近年では狭小住宅を建てる方も多くいます。
本記事では、横浜市で狭小住宅を建てる際に注意すべき点について解説します。
後悔しないためにも、ぜひご一読ください。
狭小住宅とは

狭小住宅とは、限られた狭い土地に建てられた住宅のことです。
主に地価の高い都市部や形状の特殊な細長い土地などに建てられることが多く、土地の面積が狭いため建物自体も狭小になります。
狭小住宅は床面積を最大限に活用するために、通常よりも高さを活かして3階建てなどの構造が採用されることもあります。
狭小住宅は、各階ごとに必要な機能を効率的に配置することが求められ、スペースの有効活用が重視されます。
また、屋根や壁面に工夫を凝らし、自然光や風を取り入れる設計が施されることもあるでしょう。
狭小住宅は土地の成約を受けながらも、都市部の便利さを生かした生活空間を提供しています。
横浜市で狭小住宅を建てる際の価格相場

横浜市で狭小住宅を建てる場合の価格相場は、あすなろ建築工房では、高気密高断熱の高性能で永くお住まいいただけるお住まいを提案しているため、3,000万円〜5,000万円程度を目安としています(土地代を除く)。
狭小住宅は、15〜20坪程度の土地に建てられることが一般的です。
参考に、横浜市の「横浜市統計書」によると1㎡あたりの工事予定額は約24万円とされています。
例えば、20坪(66㎡)の場合、工事費は約1,584万円です。
ただし、土地の立地や建築条件によっては割高になるケースもあるため、具体的な計画を立てる際は詳細な見積もりを取るようにしてください。
計画段階から予算と工期を考慮し、建築業者との十分な打ち合わせを行うことが建設費の見積もりの信頼性を高めるポイントです。
横浜市の狭小住宅にかかる費用の内訳

横浜市の狭小住宅にかかる費用の内訳を事前に確認しておくことも重要なポイントです。
費用の内訳を確認しておくことで、具体的な費用を確認できて必要でないコストの削減もできます。
以下では、横浜市の狭小住宅にかかる費用の内訳を解説します。
本体工事費用
本体工事費用は、家の建設に必要な主要な費用の一部です。
基礎工事や骨組み(柱や梁)、内装(床・壁・天井)、外装(外壁・窓)、屋根、さらに設備(配管・配線など)が含まれます。
とくに狭小住宅では限られたスペースを最大限に活用するため、3階建てなどの複数階建ての構造が一般的で、本体工事費の割合が相対的に高くなる傾向にあります。
本体工事費用は建築の基本的な部分を構築するために不可欠で、建物の耐久性や機能性に直結するといえるでしょう。
付帯工事費
付帯工事費は、家の建設費用以外にかかる追加費用を指します。
一般的な項目としては外構工事、屋外給排水工事、さらに必要に応じての地盤改良が含まれます。
とくに3階建ての場合、2階建てよりも地耐力が必要になるため、
同じ地盤でも地盤改良が必要となる可能性があり、費用が多くかかるため注意が必要です。
付帯工事費は住宅の敷地の状況や建築計画により異なりますが、地盤改良はとくに重要であり地盤の状態により費用が大きく変動します。
計画段階から付帯工事費を考慮して予算を設定しておきましょう。
諸費用
諸費用として、契約手数料や印紙代、登記手続き費用があげられます。
上記のような費用は一般住宅とほぼ同様であり、具体的な金額は物件価格や手続きの複雑さにより異なります。
また、引越し費用も重要な出費です。諸費用は想定外の負担となる可能性があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
予算計画を立てて、追加の費用がなるべく出ないように準備しておきましょう。
横浜市で狭小住宅を建設するメリット
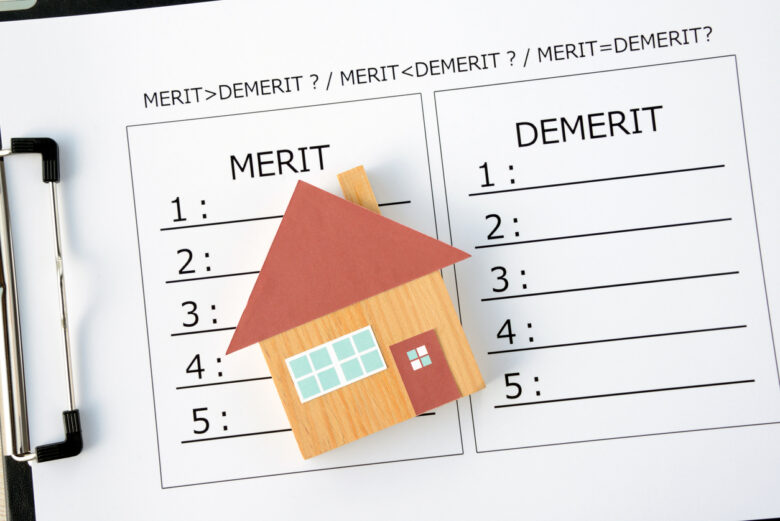
横浜市で狭小住宅を建設する場合、3つのメリットがあります。
建設前にメリットを理解しておくことで、より理想的な狭小住宅を購入できるでしょう。
以下では、各メリットについて解説します。
総費用を抑えられる
狭小住宅は、総費用を抑えられることがメリットの一つです。
狭小住宅は住宅の権利区、購入時のイニシャルコストや見物の維持に必要なランニングコストを削減できます。
一般的な坪単価は高くなる可能性がありますが、建物自体が小さいため、必要な建築資材も少なく済みます。
さらに、室内空間が狭いことで光熱費やメンテナンス費、リフォーム費も節約可能です。
総費用を抑えて都市部での住宅需要にも応えやすいため、狭小住宅は経済的かつ実用的な選択肢といえます。
利便性の高いエリアに建設できる
狭小住宅は利便性の高いエリアに建設できる点でメリットに挙げられます。
都市部に建てられる狭小住宅は、交通機関やコンビニ、スーパーなど日常生活においても不便に感じることはありません。
利便性の高さにより、日常の移動や買い物が容易に行えるため、生活コストを抑えられるでしょう。
また、交通の便が良いことで通勤や通学がしやすくなり、時間や労力も節約できます。
さらに、近隣の施設やサービスを利用することで、自宅周辺での生活の質の向上につながります。
税金を抑えられる
狭小住宅の建設は、税金を抑えることも可能です。
固定資産税や都市計画税などの税金は一般的に土地の広さや路線価に比例して課税されるため、
狭小住宅のように土地面積が小さい場合、その分税負担も軽減される場合があります。
例えば、固定資産税は土地と建物の評価額に基づいて課税されますが、
狭小住宅の土地は広さが限られているため評価額が低くなり結果的に税額も抑えられます。
ただし、都市部の場合は、
A:路線価60万/㎡ 25坪(≒83㎡) 60×83=4,930
B:路線価25万/㎡ 50坪(≒165㎡) 25×165=4,125
このように、上記は一例ですが、狭小の方が評価額が低くならない場合もあります。
同様に都市計画税も土地の評価額に依存するため、狭小住宅の土地の評価額が低い場合、
税負担が軽減されるでしょう。狭小住宅を選ぶことにより住宅の維持費用の一部である税金を節約でき、経済的なメリットも生まれます。
狭小住宅で広々と過ごすためのポイント
狭小住宅といえば狭いイメージを持つ方も多くいますが、広々と過ごすために工夫できることがいくつかあります。
以下では、狭小住宅で広々と過ごすためにできる5つのポイントを解説します。
部屋を壁で区切らないようにする
狭小住宅で広々と過ごすためには、部屋を壁で区切らないようにするといいでしょう。
壁が少なければ視界が広がるだけでなく圧迫感も薄れるため、空間が広く感じられます。
必要なときは、カーテンや可動式の壁を利用して仕切ると良いでしょう。
上記のように工夫すれば、プライバシーを確保しながら柔軟に空間を使い分けられます。
また、引き戸は開き戸に比べてスペースを有効活用でき、家具の配置がしやすくなります。
引き戸は壁の中に収納できるため、扉が空いたときに余分なスペースを取らず、室内をすっきりと維持できます。
上記のような工夫をすることで、狭小住宅でも広く快適に過ごせるでしょう。
地下室をつくる
狭小住宅で広く過ごすためには、地下室をつくるのも手段の一つです。
地下室を設けると大きなスペースを確保でき、リビングや寝室などの主要な生活空間を広々と使えます。
地下室を利用して趣味の部屋やホームオフィス、ホームシアターなどをつくることができ、地上部分のスペースを有効活用することが可能です。
また、地下室を部屋として利用するだけでなく、床下収納にすることも可能です。
床下収納を活用すれば、普段使わない季節物の衣類やアウトドア用品などを効率よく収納でき、リビングや寝室などの生活空間をすっきり保てます。
このように、地下室や床下収納をうまく活用することで、狭小住宅でも広々と快適に過ごせるでしょう。
ロフトやスキップフロアをつくる
ロフトやスキップフロアは、狭小住宅が広々と使える工夫の一つです。
スキップフロアは1つの階層に複数の高さが設けられた構造で、異なる用途の空間を一つのフロアに作り出します。
ロフトやスキップフロアを取り入れることで、床面積が限られている狭小住宅でも活用できる空間が増えます。
例えば、リビングのうえにロフトを設置することで、リビング自体も広く感じられるでしょう。
スキップフロアを取り入れることで、視覚的にも広がりが生まれて家全体が開放的に見えるはずです。
動線を意識する
狭小住宅で広く過ごすためには、動線を意識してみましょう。
生活動線とは家の中で日常的に移動するルートのことで、家事動線は家事をする際に効率的に動けるルートのことです。
動線が悪ければ、狭い空間での生活がさらに住みづらくなります。
床面積が少ない狭小住宅では、無駄なスペースが許されずに動線の設計が重要です。
例えば、キッチンからダイニング、リビングへの動線がスムーズであると日常の家事や生活が効率的に行えます。
また、動線を意識して家具を配置すると移動の無駄を減らし、スペースを有効に活用可能です。
狭小住宅でも動線を工夫することで、快適で広々とした生活空間を実現できるでしょう。
収納スペースを工夫する
狭小住宅で広く過ごすためには、収納スペースを工夫しましょう。
中途半端な大きさのクローゼットは、部屋を狭く見せるだけでなく、使いづらくなる可能性があります。
そのため、家族全員の衣類を一箇所にまとめて収納できるファミリークローゼットを設けるといいでしょう。
ファミリークローゼットを活用することで、他の部屋の収納スペースを効率的に使用でき、居住空間を広く保てます。
また、各場所に収納スペースを設ける場合は、収納量の多い家具やベッド下収納などの工夫が有効的です。
上記により、限られたスペースを活用して部屋全体を広々と過ごせるでしょう。
狭小住宅を建てる際の注意点

狭小住宅を建てる際は、事前に注意点を理解しておくことが重要です。
注意点を知ることで、未然にトラブルを防げるでしょう。以下では、狭小住宅を建てる際の3つの注意点を解説します。
建築コストが割高になる可能性がある
狭小住宅を建てる際の注意点として、建築コストが割高になる可能性が挙げられます。
狭小地は一般的には入り組んだ場所に位置しているため、
工事用の大型車両が入れるかどうか事前に確認して置くことが重要です。
とくに道路の幅が狭い場合は大型車両が進入できないため、
建築資材や機材の運搬を人力で行う必要があり、コストが高くなる可能性があります。
さらに、家の建築コストは広さに依存しない場合もあるため注意が必要です。
狭小住宅の場合、設計や施工における工夫が求められ、その分費用がかかることもあります。
建築規制を事前に確認しておく
狭小住宅を建てる際は、事前に建築規制を確認しておきましょう。
建築基準法により土地ごとに建物の広さや高さが定められており、従わないと建築許可が降りません。
とくに3階建ての狭小住宅を計画する場合、斜線制限や建ぺい率といった規制が大きな制約となります。斜線制限は建物が周囲の環境に与える圧迫感を軽減し、日照や通風を確保するために、建物の高さや形状に影響を与えます。
また、建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合を制限するものであり、それによって建物の最大の建築面積が決まります。
上記のような規制を無視すると、設計のやり直しや建築許可の遅延を招き、費用や時間が無駄になる可能性があります。
そのため、計画段階で専門家と相談し、必要な建築規制をしっかりと確認しておきましょう。
プライバシーへの配慮が必要である
狭小住宅を都市部に建てる際は、プライバシーへ配慮が重要です。
とくに都市部では家同士の距離が近くなることが多く、隣の家との視線や音の問題が発生しやすくなります。
距離を十分に確保できない場合は、防音効果のある設計を取り入れることが有効です。
例えば、壁材や窓ガラスに防音性の高い素材を使用することで音漏れを防ぎ、快適な生活空間を保てます。
また、窓の位置にも注意が必要です。
隣の家の窓や玄関と向き合わないように配置することで、視線を遮りプライバシーを守ることができます。
上記のような対策を行えば、都市部の狭小住宅でも快適でプライバシーの守られた生活を実現できるでしょう。
横浜市の狭小住宅の事例

上記の画像は、「あすなろ建築工房」で横浜市に狭小住宅を建築した事例です。
あすなろ建築工房で建てた狭小住宅は、小さいながらも子育て世代の家族が快適に過ごせるように工夫して設計されています。

家族のプライベートスペースを確保しながら、閉鎖的にならないように目線の抜けを意識した設計が練られています。
将来のご家族の変化にも柔軟に対応できるように設計されているため、長く住む際にも安心感があるでしょう。
横浜市の狭小住宅を建設する際は事前に相談しよう
本記事では、横浜市で狭小住宅を建てる際の注意点について解説しました。
狭小住宅はスペースが狭く家族向けではないのではないかと不安になるかもしれませんが、工夫を施せば広々と過ごせます。
横浜市で狭小住宅を建てたいとお考えの場合、「あすなろ建築工房」にお任せください。
一緒に理想の住宅を建てるためのサポートを行っているため、安心してご相談ください。
また、あすなろ建築工房では家づくりに役立つ情報をお届けするメルマガ配信を行っております。
家づくりをご検討している方はぜひご登録下さい。
他の記事をみる






